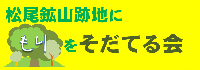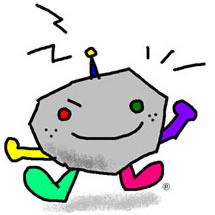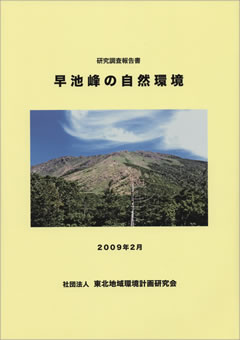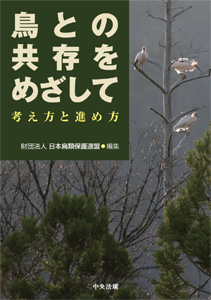研究懇話会
| 第83回研究懇話会(R7.2.14:岩手県公会堂)の講演要旨 |
|||
| (タイトル名をクリックする内容が見られます) | |||
| 岩手県におけるナラ枯れ被害状況について | 小岩俊行 | ||
| 岩手県林業技術センターにおける雲南省連携とアミガサタケの研究について | 成松眞樹 | ||
| 第68回 | 平成22年2月27日 | 北上山地の地形 | 吉木 岳哉 |
| 岩手のアカモクとその生育環境 | 高橋 清隆 | ||
| 第67回 | 平成21年10月24日 | 屋久杉の歴史と現状 | 新山 馨 |
| 土壌から知る早池峰環境の変遷2万年 | 照井 隆一 | ||
| 第66回 | 平成21年 7月25日 | 早池峰山における高山植物群落の構造と その特徴 |
竹原 明秀 |
| 登山道に沿う地形景観と地名・伝承 | 高橋 秀洋 | ||
| 第65回 | 平成21年 2月14日 | いわての森林づくり県民税について | 阿部 義樹 |
| いわての希少昆虫について | 中谷 充 | ||
| 第64回 | 平成20年12月 6日 | 岩手県植物誌にまつわる諸問題について | 沼宮内 信之 |
| 土壌生物・細胞性粘菌の生活環について | 内山 三郎 | ||
| 第63回 | 平成20年 8月30日 | 自然と人為との調和 | 村井 宏 |
| 第62回 | 平成20年 2月23日 | 岩手県のマツノザイセンチュウ抵抗性育種の進め方と進捗状況 | 蓬田 英俊 |
| 寒冷地のマツ材線虫病による年越し枯れに ついて |
市原 優 | ||
| 第61回 | 平成19年12月 8日 | 東北地方太平洋岸の温帯混交林 | 平吹 喜彦 |
| 第60回 | 平成19年10月27日 | 失われていく雪と氷の造形 | 高橋 亭夫 |
| 日本政府は日本国憲法を守れるか? | 金子 与止男 | ||
| 第59回 | 平成19年 7月21日 | サクラソウの生態について | 齊藤 政宏 |
| 岩手県のイヌワシ:繁殖率低下の現状と対策 | 前田 琢 | ||
| 第58回 | 平成18年12月 9日 | 河川の底生動物と川の生態系 | 市川 杜夫 |
| ドイツ西部の森と街を見る | 下田 一 | ||
| 第57回 | 平成18年10月 1日 | いわて環境の森整備事業について | 成田 一 |
| 北上高地「緑の回廊」について | 大菅 晴信 | ||
| 間伐の設計について | 浅沼 晟吾 | ||
| 第56回 | 平成18年 7月 8日 | コナラ種子の乾燥と芽生えの成長 | 阿部 信之 |
| シベリヤ内陸部における最終氷期以降の気候変動と植生遷移 | 志知 幸治 | ||
| 第55回 | 平成18年 2月18日 | 多量の積雪が引き起こしたアオモリトドマツの樹冠破壊について | 関 剛 |
| アオモリトドマツはなぜ多雪山地で優勢なのか | 杉田 久志 | ||
| 第54回 | 平成17年12月 3日 | 里山の自然を考える | 小澤 洋一 |
| 環境に配慮した緑化の取り組み事例 | 清水 幸憲 | ||
| 第53回 | 平成17年10月 2日 | ブナの生態 | 原 正利 |
| 第52回 | 平成17年 7月 9日 | 河川関連工事から土谷川の自然環境を見つめて | 中山 優彦 |
| 日本に於けるハナヒョウタンボクの分布と生態について | 高橋 大等 | ||
| 第51回 | 平成17年 2月 5日 | 土砂災害から地域を守るための新しい展開 | 井良沢 道也 |
| 世界遺産白神山地ブナ林の森林植生モニタリングについて | 浅沼 晟吾 | ||
| 第50回 | 平成16年12月 4日 | 化学物質過敏症における環境要因の影響について | 水城 まさみ |
| 食と住まいのトレーサビリティ | 岩泉 好和 | ||
| 第49回 | 平成16年9月25日 | 平成8年「植生復元試験」について | 下田 一 |
| 森の再生活動の課題 | 高橋 秀洋 | ||
| 第48回 | 平成16年 7月 3日 | バッタリー村20年のあゆみ | 木藤古徳一郎 |
| 生徒と守る地域の自然 | 斎藤 せい子 | ||
| 第47回 | 平成16年 2月11日 | 早池峰山の特異な地形とその成因 | 米地 文夫 |
| 土が語る 早池峰山の古代と現代 | 照井 隆一 | ||
| 早池峰山に生きる多様な植物たち | 竹原 明秀 | ||
| 第46回 | 平成15年12月 6日 | 木質バイオマス有効利用の取り組み | 遠藤 保仁 |
| 中国(扎竜)ザーロン共同研究旅行記 | 由井 正敏 | ||
| 第45回 | 平成15年 9月 6日 | 南部桐とその活用 | 八重樫 良暉 |
| 自然環境から生き方を学ぶ中学生たち | 上野 幸子 | ||
| 第44回 | 平成15年 6月28日 | ネパールの酪農と乳牛事情 | 高橋 洋二 |
| 壮大!働き盛り三代で一巡する焼畑輪作 | 古沢 典夫 | ||
| 第43回 | 平成15年 2月15日 | シルクロード「敦煌の沙漠・緑・遺跡」 | 村井 宏 |
| 岩手山火山における治山対策 | 福嶋 雅喜 | ||
| 第42回 | 平成14年12月 7日 | 岩手山の植生 | 千葉 博 |
| 環境性砒素の生体影響 | 千葉 啓子 | ||
| 第41回 | 平成14年 9月 7日 | 早池峰山域の地形 その魅力と秘密 | 米地 文夫 |
| 土は語る 早池峰山、古代の姿 | 照井 隆一 | ||
| 薬師岳のなりたち 斜面構成のプロセス | 西城 潔 | ||
| 第40回 | 平成14年 7月 6日 | 花生態学の応用的課題 | 鈴木 まほろ |
| 昆虫の胚形成 -性細胞の分化を中心として | 宮 慶一郎 | ||
| 第39回 | 平成14年 2月 9日 | 下北半島の自然 ~人の暮らしの移り変わりとニホンザルを中心に | 植月 純也 |
| 砂漠の神と森の神 ~アフガン問題に絡めて | 千葉 喜秋 | ||
| 第38回 | 平成13年11月 8日 | オシャレに生きる ~森も人も | 村田 愛子 |
| 松くい虫被害と防除 | 佐藤 平典 | ||
| 第37回 | 平成13年 9月 1日 | 衛星画像処理と地理情報 | 飯倉 善和 |
| 県民の森の四季 | 大和 敬子 | ||
| 第36回 | 平成13年 7月 7日 | レンズを通して見た自然 | 時田 克夫 |
| エゾアワビの話 | 内田 明 | ||
| 第35回 | 平成13年 2月24日 | 遺伝子組み換え体の取引に関する国際制度 | 磯崎 博司 |
| 植物から見た山火事 | 平塚 明 | ||
| 第34回 | 平成12年12月 9日 | 絶滅危惧種アツモリソウの増殖と保護に関する研究 | 小山田 智彰 |
| きのこ雑話 | 南館 昌 | ||
| 第33回 | 平成12年 9月 2日 | 頂から見えるもの | 北村 尚子 |
| 土地に生きる蝶の姿 | 根口 勉 | ||
| 第32回 | 平成12年 6月24日 | 「森林教育」研究の課題 | 比屋根 哲 |
| わたしの中国 | 国香 よう子 | ||
| 第31回 | 平成12年 1月 2日 | モンゴル環境事情 | 幸丸 政明 |
| 森林環境下における土壌の役割 | 堀田 庸 | ||
| 第30回 | 平成11年11月20日 | 消えゆくラン科植物 | 及川 邦夫 |
| こころの教育と森林 | 五十嵐 正 | ||
| 第29回 | 平成11年 9月 4日 | 岩手県自然環境保全指針について | 山瀬 宗光 |
| 林業の労働衛生 | 中屋 重直 | ||
| 第28回 | 平成11年 7月10日 | 学校における環境教育-いまとこれから- | 吉丸 蓉子 |
| 南八幡平地域に発達する湿原について | 竹原 明秀 | ||
| 第27回 | 平成11年 2月27日 | 雪氷学と地球温暖化 | 中村 勉 |
| コウモリと飛翔適応 | 横山 恵一 | ||
| 第26回 | 平成10年11月28日 | 中国福建省における自然保護区の現状と今後の自然保護政策 | 三上 進 |
| 山小屋炉辺談 | 金沢 裕臣 | ||
| 第25回 | 平成10年 9月 5日 | 環境としての岩手の景観 | 米地 文夫 |
| 岩手の地質と火山灰 | 照井 一明 | ||
| 第24回 | 平成10年7月25日 | 五葉山自然倶楽部-親しみながら・楽しみながら- | 千葉 修悦 |
| 北極スピッツベルゲン島の土壌動物群集 | 吉田 勝一 | ||
| 第23回 | 平成10年2月28日 | 石川啄木の自然観 | 山本 玲子 |
| 白神山地の自然植生 | 斎藤 宗勝 | ||
| 第22回 | 平成9年11月29日 | 北上山系のイヌワシの生態 | 関山 房兵 |
| 川を軸とした地域連携活動 | 平山 健一 | ||
| 第21回 | 平成 9年 9月 6日 | プラントオパールによる古環境推定 | 佐瀬 隆 |
| 自然地をみんなの手でみんなのものに | 上田 てい子 沢口 たまみ |
||
| 第20回 | 平成 9年 7月 5日 | エジプトとその遺跡 | 山家 敏雄 |
| 岩手山の噴火史と地形 | 土井 宣夫 | ||
| 第19回 | 平成 9年 5月24日 | 世界の環境事情[第2回公開講演会と兼ねる] | [井上克弘,近田文弘] |
| 第18回 | 平成 8年12月 7日 | 生物活用による河川の浄化とアグリツーリズムの現況 | 下田 一 |
| 賢治がみた森林・樹木 | 桜田 恒夫 | ||
| 第17回 | 平成 8年 9月 7日 | 地域開発問題 | 由井 正敏 |
| 山村活性化方策 | 岡田 秀二 | ||
| 第16回 | 平成 8年 6月29日 | 生物多様性について | 磯崎 博司 |
| マングローブ林の保全 | 照井 隆一 | ||
| 第15回 | 平成 8年 4月20日 | 自分の図書について | 高橋 喜平 |
| 第14回 | 平成 7年12月 2日 | ヨーロッパの環境問題 | 及川 幸人 |
| 水環境問題と農村のかかわり | 伊沢 敏彦 | ||
| 第13回 | 平成 7年 9月 2日 | 北上川の河川環境の現状と管理計画 | 北川 明 |
| 東北地方の治山・砂防事業での魚道の設置状況と問題点 | 石井 正典 | ||
| 第12回 | 平成 7年 6月10日 | コンピュータグラフィックスで空を飛ぼう | 横山 隆三 |
| 第11回 | 平成 7年 4月22日 | 大気環境の現状と最近の課題 | 角田 文男 |
| 第10回 | 平成 7年 1月21日 | チベット高原での水分観測 | 太田 岳 |
| 第 9回 | 平成 6年11月26日 | 森林施業の多様化 | 安藤 貴 |
| 地球環境からみた戦後の拡大造林 | 山谷 孝一 | ||
| 第 8回 | 平成 6年 7月16日 | 富士山麓の環境特性と地域開発 | 塩坂 邦雄 |
| 北上山系の大規模開発草地の将来を考える | 村井 宏 | ||
| 第 7回 | 平成 6年 4月23日 | ノルウェーの森 | 千葉 喜秋 |
| 岩手の植生 | 菅原 亀悦 | ||
| 第 6回 | 平成 6年 1月22日 | リモートセンシングによる環境解析 | 横山 隆三 |
| 第 5回 | 平成 5年 9月18日 | 森林の保健休養機能 | 比屋根 哲 大石 康彦 田口 春孝 |
| リモートセンシングの森林研究への利用 | 中北 理 | ||
| 第 4回 | 平成 5年 6月26日 | 森と水の社会経済史 | 田中 茂 |
| 岩手県自然環境保全計画 | 古澤 元雄 | ||
| 第 3回 | 平成 5年 4月24日 | 転換期の東北経済と東北振興問題 | 船越 昭治 |
| 第 2回 | 平成 5年 4月13日 | 県政の諸問題-三県総を主として | 笠水上 譲 |
| 第 1回 | 平成4年11月14日 | 岩手県の環境 | 駒井 健 |
| 宮沢賢治の一側面 | 井上 克弘 | ||